- HOME
- 【大阪開催】 日経産業新聞フォーラム 農機・建機分野における自動運転技術の最新動向
キーワード

昨今、テクノロジーの進化と同期するように農機・建機分野においても自動運転の波がきています。人手不足の解消など未来に向けてこの市場が拡大していくことは間違いありません。一方で一般的に普及するまでに技術面、安全面、法整備などの問題を抱えていることも事実です。
本フォーラムは、有識者における基調講演に加えて、自動運転技術開発を支える企業によるセッション、事例企業による特別講演により構成され、それぞれの見地から農機・建機分野における最新技術動向と展望、およびソリューションを発信いたします。
概要OVERVIEW
- 開催日時
- 2019/12/9(月)
12:30~17:10 (開場12:00)
- 会場
-
グランフロント大阪 C棟カンファレンスルーム ルーム3+4
(大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館C棟)
- 受講料
- 無料
- 定員
- 180名
- 主催
日本経済新聞社
- 企画協力/特別協賛
dSPACE Japan
- 協賛
MathWorks Japan、イネーブラー、シーメンス
- 締め切り
2019/11/28(木)17:00
- 申込者多数の場合は抽選になります。抽選の結果は、当落に関わらず11月29日(金)頃より入力いただいたメールアドレスにご連絡します。
- ご記入いただいた個人情報はご本人の承諾なく本フォーラムの実施目的以外には使用いたしません。
- 講演タイトル、登壇者、タイムスケジュールは変更になる場合があります。
- お問い合わせ
日経産業新聞フォーラム「農機・建機」事務局
◇専用電話 03-6812-1066 (10:00~17:00、12:00~13:00を除く 土・日・祝を除く)
◇専用メールアドレス sp@nikkeipr.co.jp
プログラムPROGRAM
12:30~13:20 基調講演
北海道大学大学院農学研究院 副研究院長・教授 野口 伸氏
日本農業が抱えている労働力不足は先進諸国・新興国でも共通である。農業従事者の減少、特に技術を有した人材の不足が問題になっており、国際的に車両系農業機械のロボット化はニーズが高い。現在ロボット農機は米国・欧州・中国・韓国・ブラジルなどで開発中である。本稿ではこの農業ロボットの社会実装に向けた課題と展望を論じることにする。特に土地基盤型農業で使用される無人トラクタなどのビークルロボットを概観する。
13:20~14:00 基調講演2
一般社団法人日本農業機械化協会 専務理事 氣多 正氏
我が国では世界に先駆けてロボットトラクターが市販化されるなど、農業機械が新しい時代を迎えつつあるが、無人走行で懸念されるのが第三者に危害を加える恐れである。これに関する関係者の取組みや政府施策、安全要件設定の考え方等を解説するとともに、安全性以外を含め、現行の政府のスマート農業機械普及支援策や今後の進展見込み等について説明する。
14:00~14:10 休憩
14:10~14:50 セッション1
dSPACE Japan 代表取締役社長 宮野 隆氏
100年に一度の技術革新の真っただ中にいる自動車業界において、開発効率向上と安全性確保にはモデルベース開発(MBD)は必須となっている。このMBDは農機・建機システムに今後求められる自動運転開発においても効果的な手法になるはずである。まず、MBDの特徴とメリットがどの様に一般的な制御システム開発に活かすことができたのかを説明する。更に最先端の自動運転システム、農機・建機システムへの応用事例を紹介する。
14:50~15:20 セッション2
MathWorks Japan シニアアプリケーションエンジニア 田中 明美氏
あらゆる「モノ」や「ヒト」がつながり、超スマートな社会になることは、私たちの生活に大きな変化を与えます。建機農機はその代表例と言っても過言ではありません。5Gの活用により、リアルタイムでの遠隔操作や機材管理システムの効率化が可能になり、オペレーターの負荷低減や安全性向上、機器のメンテナンスコストの削減や生産性の向上が期待されています。建機農機に5Gを活用した世界でのユースケースと、実現に必要なシミュレーション環境を分かりやすくご紹介いたします。
15:20~15:30 休憩
15:30~16:00 セッション3
イネーブラ― GNSS事業部 営業チームリーダー 千田 克志氏
「カーナビでは海の上を走ってる」と言われた時代から、現在は車・電車・飛行機までGPSでの自律制御を求められる時代です。令和元年を皮切りに、そうした業界からの強いニーズを受け、誰もが、手軽に、いつでも、安価にcm級の高精度な測位を利用できる、大きな技術革新が次々に生み出されています。本稿では測位およびそのシミュレーション技術の最新動向について説明いたします。
16:00~16:30 セッション4
シーメンス TASS本部 部長 堀田 基之氏
無人運転を実現するためには、多くの時間と費用をかけて車両テストを実施し、制御ロジックの改良を積み重ねていく必要があります。この検証作業を加速するために、弊社では、仮想空間上に車両・センサ・制御モデルを構築する最先端のデジタル化技術を提供します。AIを駆使したモデル化、設計、制御技術により車両の走行、制御、電動化、燃費に関する多性能の検証を行い、開発スピードを大幅にアップさせることが可能となります。
16:30~17:10 特別講演
キャタピラ― GCI販売促進部 中大型製品担当部長 山本 茂太氏
人口減少に直面する日本において自動化施工は、内閣府のムーンショットプロジェクトの1つともなっており、大きな課題となっています。自律運転を可能にするためにはデジタル制御が前提となるが、アニューアルアップデートなどソフトウェアによる現場での機能進化も可能なCat320次世代型油圧ショベルはデジタルプラットフォームの先駆けと位置付けられます。現在その他の機種にも展開中の次世代アーキテクチャを中心に、自動・半自動等に加え、未来の自律化施工を見据えた当社の取り組みを、世界の活用例、日本における協業などを含め、ご紹介いたします。
登壇者SPEAKERS

野口 伸氏
北海道大学大学院農学研究院
副研究院長・教授
1990年北海道大学大学院博士課程修了。農学博士。同年北海道大学農学部助手。97年助教授、2004年より教授。現在、副研究院長・教授、内閣府SIP「スマートバイオ産業・農業基盤技術」プログラムディレクター代理。その他、中国華南農業大学、中国農業大学、中国西北農林科技大学の客員教授、伊ボローニャクラブ会員。専門は生物環境情報学、農業ロボット工学。農作業の自動化・ロボット化はじめスマート農業に関する研究に従事。

氣多 正氏
一般社団法人日本農業機械化協会
専務理事
昭和53年農林水産省入省。生研機構(現農業技術革新工学研究センター)企画部長、農林水産技術会議事務局地域研究課長、北海道農業研究センター企画管理部長、九州農政局次長等を経て平成27年から現職。

宮野 隆氏
dSPACE Japan
代表取締役社長
University of California Davis校工学部機械工学科修士課程修了。ミクニ、Delphi、Boschを経て2007年にdSPACE Japanへ入社。1980年からエンジン制御プログラムをアセンブラで作成、ECUの回路設計を含めた組込みシステムを経験。その後吸気マニホールド、ハイブリッド車両等のシステムのシミュレーションを行い、メカトロニクス、シミュレーション、制御に関する業務に従事。dSPACEでは技術部長の傍らモデルベース開発(MBD)の促進のため、セミナーや大学での寄付講座等を実施。15年3月より現職。

田中 明美氏
MathWorks Japan
シニアアプリケーションエンジニア
MathWorksのシニアアプリケーションエンジニアとして、特に通信システム、信号処理、画像処理、およびHDLの実装に注力し、電子情報通信学会/スマート無線研究会(SR)の専門委員も務める。MathWorks入社前は、セルラーシステムのLSI/FPGAの設計をしており、世界初の機能を実装した経験などを持ち、書籍「MATLAB/Simulinkとモデルベース設計による2足歩行ロボット・シミュレーション」の著者の一人でもある。

千田 克志氏
イネーブラ―
GNSS事業部 営業チームリーダー
調整中

堀田 基之氏
シーメンス
TASS本部 部長
早稲田大学理工学部卒業、Bond大学にてMBA取得。30年以上に渡ってCAD/CAE業界にて営業・マーケティング活動を行う。この10年ほどは、オランダ/TASS International社が開発した運転支援システム・自動運転車両開発のためのシミュレーションツールを担当し、交通事故による死傷者ゼロを目指して活躍中。
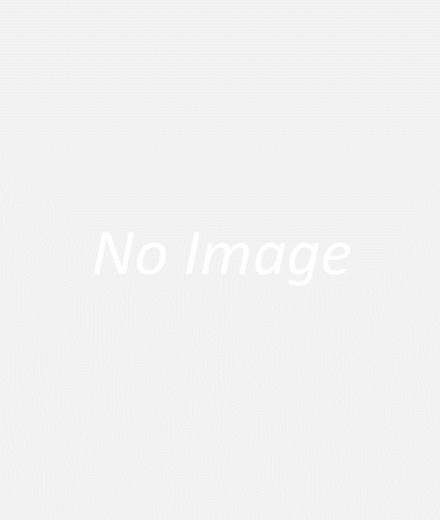
山本 茂太氏
キャタピラ―
GCI販売促進部 中大型製品担当部長
早稲田大学理工学部卒業。20年以上に渡ってCaterpillar社にて営業・マーケティング活動を行う。特に災害復旧工事などの遠隔無人化施工支援や、最近は自動/自律施工の分野でユーザとの共同開発に注力している。




