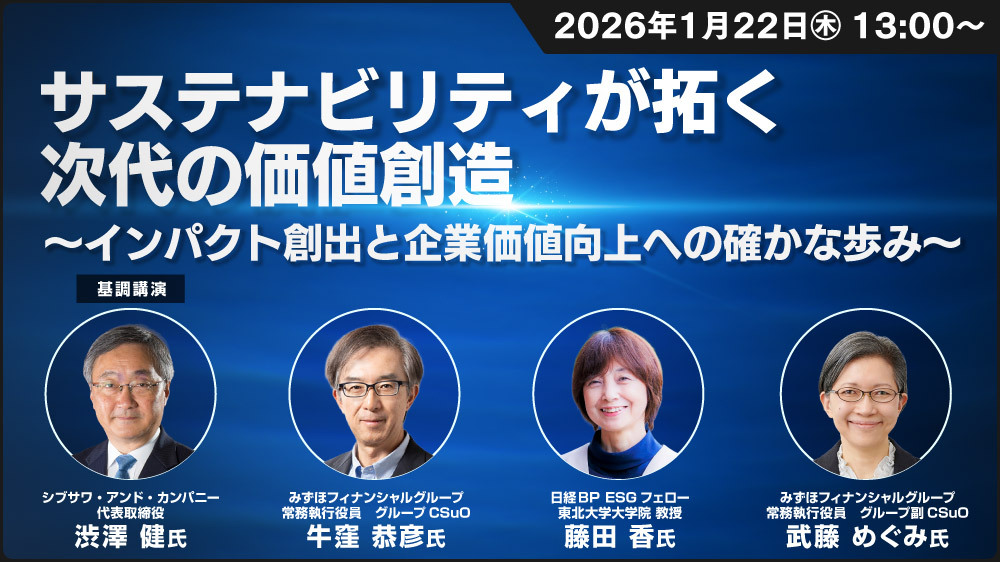- HOME
- 【オンライン開催】 NIKKEI食の未来シンポジウム

私たちにとって最も身近で必要不可欠な「食」には、世界的な食糧危機や気候変動、フードロスや農林水産業の担い手減少など、非常に多くの課題が顕在しています。また、フードテックや新たな消費スタイルの到来、多様な食文化の定着など、食産業は激動と変革の中にあります。
未来の食、そして食産業はどう変化するのか。様々な有識者・企業の皆様と議論を深め、世界中の人々が集う万博会場から発信します。
概要OVERVIEW
- 開催日時
- 2025/6/9(月)
10:30~16:00
- 受講料
- 無料
- 主催
日本経済新聞社 イベント・企画ユニット
- 協賛
クボタ、日世、日本ハム、UHA味覚糖
- 締め切り
2025/6/9(月)9:00
- 備考
事前登録いただいた方の中から抽選で 10名様に書籍『フードビジネス 最新キーワード64』(発行:日経BP)をプレゼントします。 当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。
- お問い合わせ
NIKKEI食の未来シンポジウム事務局
プログラム Program
10:30~11:00 オープニングセッション「みどりの食料システム戦略で切り拓く食と農の未来」
11:00~11:30 基調講演「食と農業のサステナビリティと新たな潮流を考える」
11:30〜12:00 セッション①「クボタのスマート農業の取り組みと将来展望」
12:00~12:45 セッション②「たんぱく質の可能性を切り拓く 日本ハムのProteinnovation(プロテイノベーション)」
日経BP 総合研究所 チーフコンサルタント 主席研究員 藤井 省吾氏
【講演概要】
日本の食文化、とりわけ私たちの健康に欠かせない良質なたんぱく質の確保は、今後難しくなると言われています。肉の分野で、日本の食のインフラを担う日本ハムが打ち出した「たんぱく質の新たな価値と未来」とは?食の領域に留まらないたんぱく質の未知なる可能性を、新技術や研究開発によって最大限に引き出し、追求し続ける日本ハム。10年後、20年後、さらにその先のたんぱく質がもたらす魅力と可能性を一緒に考えます。
14:00~14:30 セッション③「VUCAな時代における社会との協創とは?」
【講演概要】
2025年1月にトランプ氏が大統領に再就任後、世界は文字通り、VUCA(不確実性の時代)へと突き進んでいます。その結果、激動するマクロ経済影響から各国のビジネス環境にも多大な影響を与えております。このような混沌とした環境下で企業は、どのように社会と共生していくべきなのでしょうか!?まさにこの問いに対して、日世株式会社の実話をお話し申し上げます。
14:30〜15:00 セッション④「健康長寿の鍵を握る細胞の働き・オートファジー」
UHA味覚糖 執行役員 バイオ開発ディビジョン ディビジョンリーダー 松川 泰治氏
【講演概要】
健康長寿の鍵を握る細胞内の働きであるオートファジーは、日本がその研究分野の最先端であるとして世界から注目されています。本講演ではこの精緻な分子メカニズムを詳解するとともに、オートファジーを亢進する可能性が示唆される食品成分についても解説。また、研究を実装するためのベンチャー企業の立ち上げやコンソーシアムの設立などの啓発活動にも触れ、UHA味覚糖によるサプリメント提供を通した取り組みもご紹介します。
15:00~16:00 クロージングセッション「食の現在から見えてくる未来~文化と科学から考える、これからの食卓の姿~」
京都府立医科大学大学院医学研究科 教授 内藤 裕二氏
食文化研究家・料理編集者、オフィスSNOW代表 畑中 三応子氏
モデレーター
日経BP 総合研究所 客員研究員 西沢 邦浩氏
登壇者 Speaker

久保 牧衣子氏
農林水産省 大臣官房 みどりの食料システム戦略グループ グループ長
東京大学農学部卒業後、農林水産省入省。大臣官房環境バイオマス政策課課長補佐、ジェトロパリ事務所出向、食料産業局輸出促進課課長補佐、ミラノ万博日本館副館長、大臣官房政策課企画官、大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室長などを経て、2022年6月より現職。
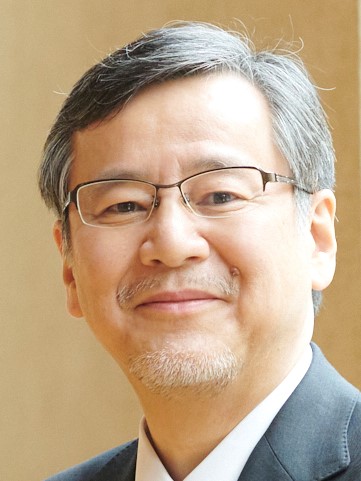
中嶋 康博氏
女子栄養大学 教授
東京大学大学院農学系研究科博士課程修了。東京大学農学部助手、同大学大学院農学生命科学研究科助教授、准教授、教授を経て、現在女子栄養大学教授。農林水産省食料・農業・農村政策審議会委員・会長代理・企画部会長、日本農林規格調査会会長、日本学術会議会員などを務める。専門は農業経済学、フードシステム学。

越智 竜児氏
クボタ 技術開発統括部 技術連携チーム 理事
1986年4月久保田鉄工(現・クボタ)入社。農機、主に田植機・野菜移植機の開発に従事、2009年移植機技術部長。2017年から計測制御技術センター所長、2021年次世代技術研究ユニット長として自動運転農機やKSAS等のスマート農業技術の開発および先行研究を推進。2022年から北米研究ユニット長兼クボタR&Dノースアメリカ社長(米国駐在)。2024年7月から研究開発統括部にて社内のスマート農業技術開発の指導および社外連携の推進を担当。

大石 泰之氏
日本ハム 執行役員(中央研究所担当)
1991年日本ハム入社。
ハム・ソーセージ部門の商品開発、技術開発、工場品質保証業務に従事。その後、中央研究所において畜産分野と食品分野を中心に基礎研究と新規事業創造を担当。食品検査技術開発や食育・栄養研究にも取り組み、2018年より培養肉など新たんぱく質やスマート養豚といった持続可能性・社会課題解決起点の研究開発を推進。20年品質保証部長、23年より執行役員として中央研究所、品質保証部、お客様志向推進部を担当。

藤井 省吾氏
日経BP 総合研究所 チーフコンサルタント 主席研究員
91年日経BP入社。医療雑誌『日経メディカル』記者、健康雑誌『日経ヘルス』副編集長を経て、2008年~13年まで6年間『日経ヘルス』編集長を務める。14年~17年3月まで、ビズライフ局長・発行人として働く女性の雑誌『日経WOMAN』、健康・美容雑誌『日経ヘルス』、共働き向けウエブマガジン『日経DUAL』、女性を応援するウエブ『日経ウーマンオンライン』を事業推進。14年には健康・医療の最新情報サイト『日経Gooday』を立ち上げた。18年4月から執行役員日経BP総合研究所副所長マネジメントソリューション局長(メディカル・ヘルスラボ所長兼務)。22年4月から現職。

岡本 明氏
日世 執行役員 経営企画部長
国内外にてマーケティング業務、新事業開発等のキャリア。
設立した国内外の子会社、JV、M&A含めて2桁以上にのぼる。
2021年8月に日世入社、理念再構築、統合ブランドロゴ再構築、本格的なブランディング開始。
その一環で24年11月より企業広告開始、国内外コミニュケーション戦略を統括。

吉森 保氏
大阪大学名誉教授、同大学院医学系研究科 Beyond Cell Reborn学寄附講座教授
1981年大阪大学理学部生物学科卒業。同大学院医学研究科修士・博士課程、私大助手、ドイツ留学を経て、96年基礎生物学研究所助教授。
大隅良典教授と共に黎明期のオートファジー分野を切り拓く。
その後、国立遺伝学研究所教授、大阪大学微生物病研究所教授、大阪大学大学院生命機能研究科及び医学系研究科教授を歴任。
2018〜22年生命機能研究科長。24年大阪大学名誉教授、25年同大学院医学系研究科寄附講座教授。文部科学大臣表彰科学技術賞、Highly Cited Researchers(6回)、紫綬褒章等受賞多数。元日本細胞生物学会会長。19年大学発ベンチャーAutoPhagyGO創業。

松川 泰治氏
UHA味覚糖 執行役員 バイオ開発ディビジョン ディビジョンリーダー
京都大学大学院農学研究科修士課程を修了。明治乳業を経て、UHA味覚糖に入社。菓子の商品開発に従事した後、ヘルスケア事業を新たに立ち上げた。基礎研究から商品開発までをつなぎ、UHAグミサプリシリーズやオートファジー習慣シリーズなどを研究開発し、商品発売による社会実装を手掛ける。2016年に執行役員に就任し、23年からはバイオ開発ディビジョン、ECディビジョンのリーダーを兼務する。社外でもオートファジーコンソーシアムの理事を務めるなど、新しいヘルスケアの在り方を追求している。

村田 吉弘氏
菊乃井 主人
京都・祇園の老舗料亭「菊乃井」の長男として生まれる。
立命館大学在学中、フランス料理修業のため渡仏。
大学卒業後、名古屋の料亭「か茂免」で修業を積む。
1976年、「菊乃井木屋町店」を開店。
1993年、菊の井代表取締役に就任。
2004年、「赤坂菊乃井」を開店。
2017年、「無碍山房 Salon de Muge」を開店。
自身のライフワークとして、「日本料理を正しく世界に発信する」「公利のために料理を作る」。また「機内食」(シンガポールエアライン)や「食育活動」、医療機関や学校訪問・講師活動を通じて、「食の弱者」という問題を提起し解決策を図る活動も行う。
2013年「和食」のユネスコ無形文化遺産への登録にも尽力した。
2012年「現代の名工」「京都府産業功労者」、2013年「京都府文化功労賞」、2014年「地域文化功労者(芸術文化)」、2017年「文化庁長官表彰」、2018年「第5回食の新潟国際賞 佐藤藤三郎特別賞」「黄綬褒章」「文化功労者」2024年「第56回食品産業功労賞」を受章。

内藤 裕二氏
京都府立医科大学大学院医学研究科 教授
1983年京都府立医科大学卒業
1998年京都府立医科大学助手,第一内科学教室勤務
2001年米国ルイジアナ州立大学医学部分子細胞生理学教室客員教授
2009年京都府立医科大学大学院医学研究科消化器内科学 准教授
2015年京都府立医科大学附属病院内視鏡・超音波診療部部長
2021年京都府立医科大学生体免疫栄養学講座 教授

畑中 三応子氏
食文化研究家・料理編集者、オフィスSNOW代表
食文化研究家・料理編集者。編集プロダクション「オフィスSNOW」代表。
『シェフ・シリーズ』『暮しの設計』(中央公論社)編集長をつとめるなど約350冊の料理書を手がけ、近現代の食を研究・執筆。
第3回「食生活ジャーナリスト大賞」ジャーナリズム部門大賞、Yahoo!ニュースエキスパート「ベストエキスパート2024」コメント部門グランプリ受賞。
著書に『熱狂と欲望のヘルシーフード』(ウェッジ)、『ファッションフード、あります。ーはやりの食べ物クロニクル』(ちくま文庫)、『〈メイド・イン・ジャパン〉の食文化史』(春秋社)など。

西沢 邦浩氏
日経BP 総合研究所 客員研究員
1991年日経BP入社。2005年より「日経ヘルス」編集長。2008年「日経ヘルス プルミエ」を創刊し、編集長に。
2016年より日経BP総研マーケティング戦略研究所主席研究員。
2018年、サルタ・プレスを設立し代表取締役。ほかに、同志社大学生命医科学部委嘱講師、ライオン歯科衛生研究所理事、日本腎臓財団評議員などを務める。
著書に「日本人のための科学的に正しい食事術」(三笠書房)ほか。